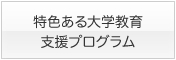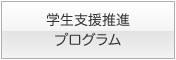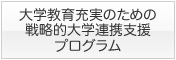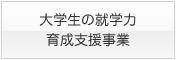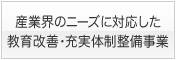本取組は、本学がこれまで行ってきたキャリア形成・就職支援を、<就業力育成支援>の観点から再構築するため、「キャリアガイダンスⅠ」(1年次・演習1単位・15回)「キャリアガイダンスⅡ」(2年次・演習1単位・15回)の科目を新たに設置し、社会的・職業的自立につながる就業力の育成支援を展開するプログラムである。
さらに高校生に対するキャリア教育及び就職5年目までの卒業生に対するリカレント教育を行い、16歳から25歳までの10年間を本学の就業力育成期間とする。
本取組の評価は、「就業力育成支援プログラム評価委員会」を学内に設置して自己評価を行う。本学は毎年、「地域参画推進連絡協議会」を設置し、久留米市長をはじめ行政関係者や商工会議所会頭による外部評価を受けている。本取組の「就業力育成支援10年間継続プログラム」も外部からの評価を受けPDCAサイクルを展開する。
入学定員180名、教員数26名の小規模短期大学である本学は、少人数制によるきめ細やかな指導のため、クラス担任制を設け、学生生活支援委員会が担任業務の企画・調整を行っている。さらに、クラスを10名程度のグループに分け、教員全員がグループのチューターを務めている。チューターは履修指導や学生生活支援、キャリア形成や就職支援を学生に行い、学生の2年間の就学を共にしている。本取組においては、チューターが受け持ちグループの学生のポートフォリオを把握・点検し、学生の個性・能力を把握し、グループガイダンスや個別カウンセリングを行い、学生の主体的な大学生活の組み立てや学習を支援する。
以上が本取組における本学の有機的連携体制である。
本取組の有機的連携体制
教授会
就業力育成支援会議 就業力育成支援推進室
教務部 学生部 就職部 学生生活支援委員会 高大連携推進室
担任 チューター
○学科の人材養成の目的
アドミッションポリシーの掲載。
○授業科目の名称・内容
カリキュラムやコース内容の説明及びカリキュラムポリシーの掲載。
○入学者・在学者・卒業者に関する情報
入学者・在学者の情報の掲載。
卒業生の進路(就職・進学)の掲載及びディプロマポリシーの掲載。
○取組パンフレットによる公表
本取組の趣旨・内容を記したパンフレットを作成し(8月)、企業・高校・地域に配付する(9月)。記載項目は、本取組の趣旨・内容及び就業力育成に関する大学の情報(学部等の人材養成の目的、授業科目の名称・内容、入学者・在学者・卒業者に関する情報等)である。
○ウェブサイトによる公表
本学ウェブサイトにおいて、本取組の趣旨・内容を載せたウェブページを作成し、(8月)、取組の展開に応じて継続的にデータを更新する。記載項目は、本取組の趣旨・内容及び就業力育成に関する大学の情報(学部等の人材養成の目的、授業科目の名称・内容、入学者・在学者・卒業者に関する情報等)である。
○学校誌・学院誌による公表
本学の学校誌において、本取組の趣旨・内容を載せる(12月)。記載項目は、本取組の趣旨・内容及び就業力育成に関する大学の情報(学部等の人材養成の目的、授業科目の名称・内容、入学者・在学者・卒業者に関する情報等)である。
○新聞による公表
地方新聞誌において、本取組の趣旨・内容を載せる(11月)。記載項目は、本取組の趣旨・内容及び就業力育成に関する大学の情報(学部等の人材養成の目的、授業科目の名称・内容、求人方法・就職状況に関する情報等)である。
○年次報告書による公表
年次報告書において、本取組の趣旨・内容を載せる(23年5月)。記載項目は、本取組の趣旨・内容及び就業力育成に関する大学の情報(学部等の人材養成の目的、授業科目の名称・内容、求人方法・就職状況に関する情報等)である。
○取組報告書による公表
取組最終年度に本取組を総括した報告書を作成し、企業・高校・地域及び大学・短期大学に配付する。
しかし、学生の就業力向上の観点から、次のような課題が認められる。
(ア)自分の適性・資質が不明で将来の見通しを持たない入学。
(イ)職業観や勤労観を持たないまま漠然とした意識での学修。
(ウ)短期間での性急な就職活動と社会人になる自覚の不足。
(エ)2年間という短期間での社会人基礎力養成のあり方。
(オ)早期離職や就職先とのミスマッチを防ぐ方策の必要性。
進路ガイダンス、資格・免許に関する講座、職業理解に関する講義、職業体験の提供等の高大連携キャリア形成支援事業を行い、高校生に対する就学力育成を行う。
(イ)大学生に対して
「キャリアガイダンスⅠ」「キャリアガイダンスⅡ」の科目を2年間にわたり設置し、他の専門科目等と関連付けることによって以下の目的を果たす。
○職業観・勤労観の確立や将来や生き方の展望を持つ。
○進路と学修を統合した主体的学びに必要な意識や能力を持つ。
○社会人及び職業人に必要な能力・態度・使命感を持つ。
○適切な就職活動ができる技術と採用試験に必要な知識・能力を持つ。
(ウ)就職した卒業生に対して1年目・3年目・5年目にキャリアガイダンスを行い、発展的自己学習の方法、職業人としての使命、キャリアアップの手法等の支援プログラムを実施する。
達成目標=1年次終了時に希望職種・業種を80%の学生が決定する。
*従来、1年次終了時には半数の学生しか進路が絞り切れていないため。
(イ)社会的・職業的な自立に向けての意識・意欲を持つ。
達成目標=就職希望率85%を達成する。
*昨年12月の短期大学生の就職希望率(全国平均)は79.0%しかないため。
(ウ)社会的・職業的な自立に向けて必要な能力・技術を持ち自己実現を行う。
達成目標=就職内定率90%、希望業種就職率85%、希望職種就職率85%、第一希望就職率75%、を達成する。
*平成22年2月1日の短期大学女子学生の全国平均就職率は67.3%のため。
(エ)社会的・職業的に自立し、地域社会に貢献し自己実現を図る。
達成目標=早期離職率20%以下を達成する。
*現在、4年生大学卒の3割、短期大学卒の4割が卒後3年以内に離職するため。
(オ)職業人として求められる能力を形成したか自ら確認する。
達成目標=取組による学生自身の成果についての達成度85%取組についての学生の満足度85%を達成する。
*学生の自己評価・満足度を高める必要があるため。
(カ)卒業生の社会人基礎力を保証する。
達成目標=就職先による評価を各項目2ポイントアップする。
*就職先へ毎年行っている卒業生のアンケートの各14項目をアップさせる。
本取組は、従来、就職部及びキャリア形成推進室が、教育課程外での取組として実施してきたキャリア形成・就職支援の活動を、就業力育成支援の観点から再構築し、大学内の連携及び大学外の連携を通じ、2年間を通して社会的・職業的自立につながる就業力の育成を図る教育課程内の取組である。
さらに、以下の要因から高校生や卒業生に対するケアも計画する。
○就業力育成という観点から短期大学の2年間という期間は短いこと。
○職業意識等を持たずに入学する学生が少なからず見受けられること。
○卒業生の早期離職の防止やキャリアアップ教育が必要であること。
以上のことから、本学は高校1年生の16歳から就職後5年目の25歳までの10年間を本学の就学力育成支援期間と考える。このようなことから、本学は本取組を学生の社会的・職業的自立を図るための大学教育改革と位置付け、学長のマネジメントのもと、就職部及び就業力育成支援推進室が企画・調整し、教職員全員の参画により取組むものである。
(イ)国公立を通じた大学の教育改革プログラムとの関係
○特色ある大学教育支援プログラム(平成16年度採択)
取組名称が「地方都市における地域参画型短期大学教育」である本選定取組は、教職員や学生が地域に参画し貢献すると共に、地域の教育力を短期大学教育に取り入れることにより、学生の人格的成長を支援し、教育・研究活動の質の向上を図る取組である。本取組を機に設立された「地域参画推進連絡協議会」は久留米市・産業界・本学を結ぶシステムであり、今回の申請取組でも大学外の連携を推進するものである。
○大学教育・学生支援推進事業(平成21年度採択)
取組名称が「卒業生のマンパワーを活用したキャリア形成・就職支援プログラム」である本選定取組は、卒業生の人的資源を活用し、卒業生の教育力と本学の教育力の統合・協働を図り、学生のキャリア形成及び就職支援の高度化を目指す取組である。本選定取組の終了期間後も、本申請取組のプログラムとして発展的に組み入れる予定である。
○戦略的大学連携支援事業(平成21年度採択)
取組名称が「地域共創のための高度人材育成基盤整備」である本選定取組は、久留米市内の5高等教育機関が地域高度人材育成事業を推進するための取組である。加盟大学が協働した就業力育成支援事業の展開やサテライト施設を使用した就業力育成支援プログラムなどを、「高等教育コンソーシアム久留米」に提案する予定である。
(ウ)取組の具体的内容(資料14頁に概念図掲載)本取組は、「キャリアガイダンスⅠ・Ⅱ」による2年間を通した社会的・職業的自立に向けた就業力育成プログラム、高校生に対するキャリア形成支援、卒業生に対する就業力支援、の3つの段階を持つ。
○「キャリアガイダンスⅠ」(演習1単位・全学科の1年次に設置・15回)
以下のテーマで授業を展開するとともに、チューターによるガイダンスを受ける。
*自己発見と社会人基礎力
自己の能力・資質を正確に自覚し、将来の展望を持った意欲的学修を展開し、基礎的なリテラシーや能力を形成するため、適性検査・自己表現スキル・作文問題・常識問題・コンピテンシー診断などを内容とする。
*職業・勤労観の形成とキャリアデザイン
自己と社会をつなげて考え、職業理解・勤労意欲を持ち、自己の人生を社会的・職業的生活の中でデザインする能力・意識を培うため、キャリア形成講演・職種業種理解・キャリアプラン討論・キャリアマップ作成などを内容とする。
○「キャリアガイダンスⅡ」(演習1単位・全学科の1年次に設置・15回)
以下のテーマで授業を展開するとともに、チューターによるガイダンスを受ける。
*自己実現力の形成
就業を通して自己実現を果たす能力・意識を培い意思決定力を身につけるため、インターンシップの活用・グループワーク・就職活動計画作成・エントリーシート作成・企業研究・就職先決定後講習などを内容とする。
*就職活動力の獲得
就職活動に必要な能力・知識・習慣を身につけるため、面接講座・マナー講座・メイクアップ講座・筆記試験対策・履歴書作成・企業情報検索などを内容とする。
○高校生に対するキャリア形成支援
高校1年生から3年生までを対象に、出前講義・講演、本学での講座・セミナー、職場体験プログラムなどを実施する。内容は、キャリアプラニング、資格と免許、職業とは、進路選択のアドバイス、短期大学生との懇談、などであり、高大連携協定校とは教育課程内で単位化してキャリア形成支援を展開する。
○卒業生に対する就業力支援
卒業後、1年目・3年目・5年目の卒業生にセミナーを開催する。1年目の卒業生には、社会人としての自覚・マナー、グループワーク・グループ討議、3年目の卒業生には、プレゼンテーション技術、専門技術・能力の開発、5年目の卒業生には、中堅職業人としての自覚と役割、教育力の養成、スキルアップ手法の研究、などを講演・演習・グループ研究などの形式で1日を使い実施する。
○「キャリアガイダンスⅠ・Ⅱ」のシラバス作成(資料15頁に素案掲載)。
○キャリアガイダンス・ラーニングポートフォリオ作成。
○本取組の広報 パンフレット作成・配付。ウェブサイト上の公表。学院誌・大学誌上の公表。新聞誌上の公表。
○高校生への取組 キャリア形成・就職支援講座の開催。
○本取組の自己評価 就業力育成支援推進室・教授会・学長が実施。
○教材開発 DVDの作成。教科書のプラニング。
○研究 取組に関する研究・調査。
○カウンセリング室の施設・設備充実。
○就職先アンケートの実施(毎年次)
(イ)平成23年度○「キャリアガイダンスⅠ」の講座開講
○本取組の広報 22年度に同じ。
○高校生への取組 22年度に同じ。
○自己評価・他外部評価 自己評価に加え、地域参画推進連絡協議会において外部評価を受ける。
○研究及び教材開発 22年度に同じ。テキストの編集・印刷・配付。
○卒業生に対する就業力育成支援 卒業1年目の卒業生にプログラムの実施。
(ウ)平成24年度○「キャリアガイダンスⅠ」「キャリアガイダンスⅡ」の講座開講
○本取組の広報 22・23年度に同じ。
○高校生への取組 22・23年度に同じ。
○自己評価・他外部評価 3年次終了後に総括的自己評価・他者評価を実施。
○研究及び教材開発 22・23年度に同じ。テキストの編集・印刷・配付。
○卒業生に対する就業力育成支援 23年次に同じ。
(エ)平成25年度○「キャリアガイダンスⅠ・Ⅱ」の内容の全面的見直し
○キャリアガイダンス・ポートフォリオの見直しと作成。
○本取組の広報 広報活動の見直しと実施。
○高校生への取組 高大連携プログラムの見直しと実施。
○自己評価・他外部評価 評価項目・方法・体制の見直しと実施。
○研究及び教材開発 教材・テキスト等の見直しと実施。
○卒業生に対する就業力育成支援 1年次及び3年次の卒業生に実施。
(オ)平成26年度○最終年度総括的評価 上記の取組に加え、最終年度総括的評価を実施。
本学が開催する地域参画推進連絡協議会の外部メンバーは、久留米市長・副市長・教育長・各部長などの行政及び商工会議所会頭・同専務などの産業界のメンバーであり、本連絡協議会で取組の趣旨・経緯・成果を説明し評価を受け連携を行う。
(イ)「高大連携協定」による高等学校との連携
高校生を対象とするプログラムにおいては、6校の高校と結んだ高大連携協定に基づき、高大連携推進室が高校生に対するキャリア形成支援事業に参画する。
(ウ)「高等教育コンソーシアム久留米」による大学間の連携
大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラムの選定を機に設立されたコンソーシアムとサテライトを利用して大学間の連携を行う。
入学定員180名の小規模短期大学である本学は、クラス担任制を設け、学生生活支援委員会が担任業務の企画・調整を行っている。さらに、クラスを10名程度のグループに分け、教員全員がグループのチューターを務めている。本取組においては、チューターが受け持ちグループの学生のポートフォリオを把握・点検し、学生の個性・能力を把握し、学生の主体的な大学生活の組み立てや学習を支援する。
「就業力育成支援プログラム評価委員会」を設置する。評価委員会は取組に対して評価を行い学長に提出する。学長は提出された評価を教授会に諮り、全学的な総括的評価を行い、理事会及び評議員会に報告する。
(イ)外部評価の体制
学長は理事会・評議員会に諮った取組の自己評価を、本学が設置している「地域参画推進連絡協議会」において報告し、学外メンバー(久留米市長・副市長・各部長・教育委員長及び商工会議所会頭等)によって、本取組の目的・内容・方法・成果について評価を受ける。
(ウ)改善策の策定システム
学長は自己評価・外部評価の結果を受け、取組に関する改善策の計画を就業力育成支援推進室に指示し、就業力育成支援推進室は改善策を計画し就業力育成支援会議に提出し、最終的に教授会にて次年度の計画を決定する。
(エ)取組期間終了時及び終了後の評価の体制及び計画
取組期間終了時に5年間の総括的自己評価を行い、外部評価を受け、取組の趣旨・経過・成果・評価及び終了後の取組計画を報告書にまとめ配付する。
取組期間終了も取組期間中の自己評価・外部評価の体制を維持する。
本取組の目的・方法・内容・成績評価等について学生にアンケートを行うとともに、取組における自らの目標達成度について項目ごとに自己評価を行う。
(イ)チューター・就業力育成支援推進室による評価
学生の目標達成度の評価に関しては、「就業力育成ポートフォリオ」を作成し、基礎資料とする。取組の目的・方法・内容の評価に関しては、就業力育成支援推進室が担任・チューターの評価を取りまとめ報告書を作成し、「就業力育成支援プログラム評価委員会」に報告する。
(ウ)「就業力育成支援プログラム評価委員会」による評価
学生による評価、チューターによる評価、就業力育成支援推進室による評価を受け、「大学教育推進プログラム評価委員会」は、本取組によって、「学生が社会的・職業的自立につながる就業力をしっかり身につけた」かどうか観点に、本取組の達成目標と照らし合わせて評価を行う。
(エ)学長による評価
学長は「就業力育成支援プログラム評価委員会」の評価に加え、建学の精神及び教育理念の観点から評価を行い、理事会・評議員会に諮り、「地域参画推進連絡協議会」に報告する。
(オ)「地域参画推進連絡教授会」の評価
「地域参画推進連絡協議会」の外部メンバーは、地域における本学の教育使命の観点から取組の評価を行い改善策を提言する。
(カ)就職先のアンケート
本学が平成19年度から毎年度実施している就職先へのアンケートを本取組の評価資料とし、3年目・取組期間最終年度の総括的評価に使用する。
○設備備品費
個別カウンセリング室設置のための費用である。学生のプライバシーに配慮した環境整備が必要なため(従来はパーティションで区切っていた)。
○旅費
調査・研究のための出張旅費である。
○人件費
取組にかかわる講師謝金・アルバイト雇用費用である。
○事業推進費
取組の広報・公開のための費用及び教材・テキスト作成費用である。